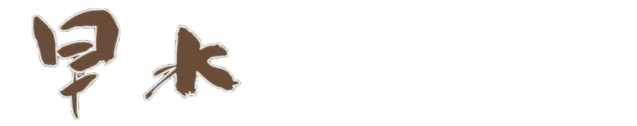2024.11.23
琉球びんがたとは
琉球びんがた(りゅうきゅうびんがた)は、沖縄県首里市周辺で作られている染織品です。その起源は14世紀から15世紀の琉球王朝時代にまで遡り、王族や士族などの婦人が礼装として着用していました。
色鮮やかな染色模様の「紅型(びんがた)」と藍色だけを使用した藍染め模様の「藍型(あいがた)」に区別されます。また、それぞれの型も技法により、型紙を使用する「型付け」とフリーハンドで模様を描く「筒引き」に分かれています。型付け染めは着尺(きじゃく)や帯、筒引き染めは引幕や風呂敷などの染織品が作られてきました。
琉球びんがたの特徴は、南国ならではの豪華な色合いと大胆な色使いです。模様は古典的な柄から近代的な柄まで多種多様で、沖縄の自然には存在しない模様も多く含まれています。
特に古典柄は、日本本土をはじめ中国や東南アジアの影響を受けた模様も少なくありません。色鮮やかな琉球びんがたは、沖縄の自然に融合しながら、先人達により受け継がれる神秘的な染め物です。