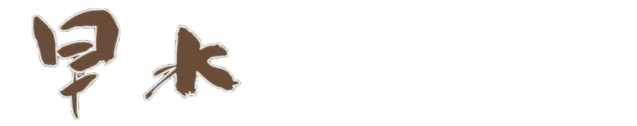2025.04.06
常滑焼とは
常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市周辺で作られている陶器です。平安時代の後期に誕生した伝統工芸品で、日本六古窯(にほんろっこよう)の一つとされていて、中世の時代から長く生産されている陶磁器として知られています。
常滑焼の特徴は知多半島で採れる鉄分を多く含んだ陶土を使用している点です。その性質を活かして、鉄分を赤く発色させることを朱泥(しゅでい)と言い、常滑焼を特徴付ける色の焼き物ができました。
茶碗や植木鉢など様々な製品が作られていますが、その中でも急須は、鉄分がお茶の苦みや渋みをまろやかにすると言われていて現代でも愛用されています。
愛知県の知多半島の丘陵地に多くの窯があり、古来より伝統技術を有した職人によって制作されてきました。質の高い製品を作る職人たちが、1,000年の歴史のなかで技術を受け継ぎ、「手ひねり成形」などの技法を伝承しています。平安時代から使われる手ひねり成形の中でも、「ヨリコ造り」は大きな壷など大物の製品を制作するときに用いられる手法です。ほかにも盆栽鉢を作るときの「押型成形」、電動ロクロを使う「ろくろ成形」などがあります。